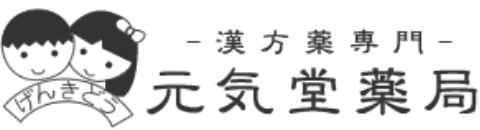VOL.215 夏の養生法
漢方では、夏は陽気が非常に強い季節とされています。火の臓腑であり、五臓の中では、「陽中の陽」と呼ばれる「心」の養生が大切な時期です。
また、漢方の聖典の一つである『黄帝内経素問』の四気調神大論には、
「夏三月、此れを蕃秀と謂う。天地の気交わり、万物華さき実る。夜に臥し早く起き、日を厭うことなかれ。志をして怒ること無からしめ、華英をして成秀せしめ、気をして泄らすを得さしめ、愛する所をして外に在るが若くせしむ。此れ夏気の応、養長の道なり。これに逆えば則ち心を傷り、秋に痎瘧となり、収に奉ずる者少なく、冬至らば、重ねて病む。」と書かれており、夏の養生を怠ると、心の気を損傷し、秋になって瘧疾を生じ、秋の時令である収斂の気に適応できず、冬には更に病を発症するとされています。
1.冬病夏治
「冬病夏治」とは、冬に起きやすい病気を夏に治療して予防するという意味で、一年で最も暑い時期に、体内の寒気を追い出すことで、冷えによる陽気不足の体質を改善し、寒さにより発症・悪化しやすい関節痛・喘息・胃腸の不調・寒冷蕁麻疹・・・等々の予防を行う方法です。暑い時の水分補給は大変重要ですが、冷たい物の摂り過ぎや過度な冷房などは冷えを増長し、体調を崩します。
2.夏の睡眠
前述の『黄帝内経素問』の四気調神大論では「夜に臥し早く起き、日を厭うことなかれ。・・・」とあり、夏は他の季節より少し早起きし、日の長さを厭わず、イライラして怒ることが無いようにと書かれています。暑さでイライラしやすい夏に精神的な安定を保つことは、火の臓腑である「心」の養生には、大変重要です。また、早起きして、涼しい早朝のうちに行動するのも良い対策の一つですね。
3.夏の食べ物
漢方では、夏は火の季節であり、五臓では心の養生が大切といわれています。心を養う食材としては、ユリネ・ハスの実・黄ニラ・リュウガン・牡蠣・あん肝・ヒジキ・アーモンドなど、暑さ対策としては、スイカ・緑豆・キュウリ・トウガン・トマト・セロリ・トウモロコシ・インゲン豆・フジマメ・ハトムギなどが挙げられます。菊花茶やハブ茶も熱を冷ましてくれます。
もちろん、「冬病夏治」の観点から冷やしすぎは禁物です。鶏肉・羊肉・桃・カボチャなどの温性の食材も臨機応変に取り入れましょう。
屋外はムシ暑く、屋内は冷房などで冷えて、体調を崩しやすい季節です。漢方の知恵を利用して、元気に乗り切りましょう。