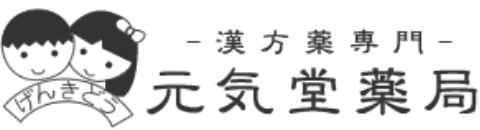漢方薬通信VOL.228 高プロラクチン血症を伴う不妊
不妊の漢方相談には、高プロラクチン血症といわれている方もいらっしゃいます。プロラクチンは、乳汁分泌ホルモンとも呼ばれ、出産後、授乳期間中に母乳を作るホルモンです。そして、授乳期間中の妊娠は、母体への負担が大きいので、プロラクチンの分泌が活発な間は、自然と妊娠しにくい状態になります。授乳期間中でないのに血中のプロラクチンが多い状態を高プロラクチン血症といい、乳汁漏出したり、排卵が抑制されて妊娠しにくくなったり、妊娠しても子宮収縮して流産してしまうことがあります。
32才のAさんは、結婚したばかりですが、もともと月経周期が不安定なので、婦人科を受診したところ、高プロラクチン血症といわれたそうです。
「初潮は15才。月経周期は、35~45日で一定せず、60日くらいになるとホルモン剤を服用して月経を起こしている。月経期間は7日間。経血の量はふつうで、血塊は無く、色は淡紅色。月経痛は、2日目に重だるい痛みがあり、温めるとラクになる。月経前には、胸が脹り、イライラすることもあるが、不安を感じることが多い。ストレスを感じやすく、ストレスが強いと月経周期が長くなる。疲れやすい。睡眠状態が悪く安定剤を常用している。」とのことでした。
肝気鬱結に心血虚を伴っていると考え、逍遙散と帰脾湯を服用していただき、腎精を補うために、鹿茸製剤も併用していただきました。服用開始してまもなく妊娠しましたが、この時は残念ながら流産。さらに漢方薬を続けて約10ヶ月。月経周期は安定して、睡眠の状態もかなり良くなってきたところで、再び妊娠。妊娠中も、体調に合わせた漢方薬を服用して、健やかに過ごされました。心配していた“妊娠中の安定剤”を服用せずにすみ、無事、かわいい女の子が誕生しました。育児も授乳も睡眠も順調で、嬉しそうな笑顔です。
漢方の古典に高プロラクチン血症という記載はありませんが、肝や腎の失調により、ホルモンバランスが乱れることがあります。一方、高プロラクチン血症は、視床下部・下垂体障害や下垂体腺腫から起こるケースや、薬剤が原因で起こるケースもあります。それらを確認した上で、月経の状態や体質などをよく見極めて、適した漢方薬をセレクトし、妊娠しやすいコンディションに近づけていきましょう。