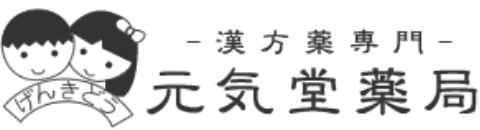元気堂の漢方薬通信
VOL.37 不妊
『中医症状鑑別診断学』によると、「妊娠適齢な女性が避妊を行わずに、結婚後3年以上妊娠しないこと」または、「過去に妊娠歴があって避妊せずに3年以上妊娠しないこと」を不妊(漢方では不孕(ふよう)といいます。)としています。前者を「原発性不孕」後者を「継発性不孕」といいます。
「26歳の主婦の方、結婚後3年ほど経つが子供ができない。月経周期は35日くらい。月経時に下腹部や乳房が張って痛い。経血に塊があることがある。イライラや不安感も強く、周囲に子供のことを聞かれるのが苦痛である。」とのこと。肝気鬱結証に血虚証を兼ねていると考え、「逍遙散」と「四物湯」を服用していただきました。3ヶ月ほどで月経周期や精神状態も安定し、下腹部痛も感じなくなりました。半年ほどでめでたく妊娠。現在は元気な男の子のお母さんです。
漢方では不妊を月経や全身の症状から、「腎陽虚証」「腎陰虚証」「気血両虚証」「肝気鬱結証」「痰湿証」「血オ証」などに分類し、それぞれに応じた三十ほどの処方を組み合わせていきます。また、これといったトラブルが見当たらないのに妊娠しない場合には、月経周期を「月経期」「低温期」「排卵期」「高温期」に分割し、時期ごとに漢方薬を服み分ける「漢方周期療法」を用います。
上記の方のようなストレスによる「肝気鬱結証」では、周囲の発言も大きく影響します。何でもないつもりでも、「お子さんはまだ?」といった不用意な言葉は慎みたいものです。