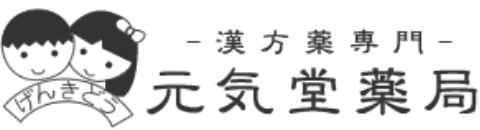アレルギー性 鼻炎
鼻に侵入してきた特定の物質(抗原)を自分以外の物質(異物)と判断すると、それを無害化しようとする反応(抗原抗体反応)がおこります。その結果、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が出てくる病気をアレルギー性鼻炎といいます。その中で、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となって、アレルギー症状を起こす病気を花粉症といいます。季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれています。
アレルギー性鼻炎は、漢方では「鼻鼽(びきゅう)」といい、先天不足(体質の虚弱)、臓腑虚損、感受外邪などにより、鼻流清涕(透明な鼻水)、噴嚏(くしゃみ)、鼻塞、流泪(涙目)、目痒、咽痒、鼻痒等を主症状とするものを指します。別名「鼽」「鼽鼻」「鼽悌」「鼽水」等とも称します。ちなみに鼻流濁涕のものは「鼻淵」といいます。
鼻と五臓との関係
鼻は五臓の中では、特に肺、脾、腎と関係しています。
1.肺
肺は五臓の中で、最も鼻と関係が密接です。
漢方の重要な古典である《素問・陰陽応象大論》に
「肺は鼻を主る。……竅に在りては鼻となる。」
とあり、鼻は肺の外竅であることを示しています。鼻は気体出入の門戸であり、下は肺に通じ、肺の呼吸を助けています。また、こちらも重要な古典である《霊枢・脈度篇》には
「肺気は鼻に通じ、肺和すれば則ち鼻能く臭香を知る。」
と書かれています。
これは、鼻の嗅覚が、正常に働くのは、肺気の通調に依存していることを示しています。肺は気を主り、宣発・粛降を司ります。ですから、肺の機能が正常ならば、精気、衛気を清竅に上注し、鼻竅は濡養、護衛、通利され、正常に働きます。肺の気が不足した肺気虚では、腠理粗鬆、衛外不固により外部からの刺激(花粉、ほこり、温度や湿度の変化等々…)に反応し易くなり、鼻鼽をはじめ、種々の鼻病を引き起こしやすくなります。また、肺の潤いが不足した肺陰虚では、鼻竅が濡潤を失い、鼻内粘膜が干燥枯萎し嗅覚が低下します。
2.脾
鼻は面部中央に位置し、鼻の中央には、鼻准(鼻柱)が位置しています。漢方で用いる経絡ではこの部位は脾に属します。また、脾は運化を主り、気血生化の源であり、肺気の充実は、脾気の充盈に支えられています。また、鼻は清気の通路であり、清竅の通利は、脾胃の昇清降濁に助けられています。
前述の《素問・玉機真蔵論》に
「脾は孤蔵たりて、中央の土以て四傍に潅ぐと言う。其の大過なると不及なると、其の病皆にいかん。岐伯曰く、大過は則ち人をして四支挙がらざら令む、其の不及は則ち人をして九竅通ぜざら令む。」
とあり、脾の機能が低下すると、気血の生化が不足し、精微が上輸されず、鼻竅が濡養されないと鼻病を発生します。
3.腎
腎は精を蔵し、肺陰、腎陰は相互に滋養し合っており、鼻竅は肺腎の滋養により生理活動を保持しています。肺は気を主り、気の根本は腎に在ります。鼻は気体出入の門戸であり、肺が呼吸を司り、腎が納気を主ることにより、鼻の気体出入の生理機能が成り立っています。このような関係のため腎の虚衰から、鼻病を引き起こすことがあります。
《素問・宣明五気論》に
「五気の病む所。心は噫をなす。肺は咳をなす。肝は語をなす。脾は呑をなす。腎は欠をなし、嚏をなす。」
とあり、腎気虚から肺気虚に至り、外界からの刺激を受け易くなり、鼻病を生じたり、腎陰不足から虚火上炎して鼻病となることを示しています。
漢方的なアレルギー性鼻炎の原因と発生のしくみ
アレルギー性鼻炎の発生の基本的なメカニズムは、肺気・肺陽の不足や鼻竅の濡養不足に外部からの刺激(花粉、ほこり、温度や湿度の変化等々…)が加わった状態です。
ここに、ストレスや胃腸虚弱、飲食の不節制などによる水分代謝の低下などが関わっています。
- 外部からの刺激(花粉、ほこり、温度や湿度の変化等々…)により肺の宣発粛降を失調させ、鼻鼽を発生します。
- 体質の虚弱による先天不足(気虚・陽虚・血虚・陰虚)のため虚熱を生じ、鼻竅を上犯して鼻鼽を生じます。
- 肺気(肺陽)不足により肺の宣発・粛降の失調を生じるとともに、衛外不固による外邪の感受容易、また固摂低下などから鼻鼽を引き起こします。
- 脾気(脾陽)不足により気血の生化不足を生じ、清陽不昇となり鼻竅失養を引き起こし、外邪を感受しやすくなり、鼻鼽を生じます。
- 肺陰や胃陰、腎陰の不足により、滋潤・粛降の機能が低下し、鼻竅が濡養されず鼻鼽を生じます。
- 精神刺激により肝の疏泄機能が失調し、気機が鬱滞して肺気の宣発・粛降機能に影響して鼻鼽を発生します。
- 飲食不節や精神抑鬱などにより生痰し、肺に上犯することにより肺失宣降となり鼻鼽を起こします。
- 腎陽の不足により気化が低下し、水飲が内停したり、また腎陽虚のため肺の陽気を補えずに鼻鼽となります。
- 病の長期化や誤治により、瘀血や気血両虚を併発していることもあります。

「アレルギー性鼻炎」や「花粉症」には、日本では小青竜湯(しょうせいりゅうとう)が有名で、服用したことがある方も多いと思います。しかし、本来漢方治療は個々の症状・体質によって異なり、様々な処方を用います。小青竜湯は「風寒束表・水飲内停」というパターンで「鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目の痒み」などの症状の他に「悪寒発熱、汗が出ない、咳嗽、呼吸困難、稀薄な痰が多い、口渇はない。或いは身体が重だるかったり、浮腫んだりすることもある。」という時に用います。小青竜湯が奏効するパターンは「アレルギー性鼻炎」や「花粉症」全体の一割にも満たないのではないかと思います。それ以外の方は、他の処方の適応となります。
「アレルギー性鼻炎」を治療する上で、他の疾患同様、病名にとらわれずに、漢方的に分類することが、最も重要となります。当薬局では、花粉症を大きく二十三のパターンに分類し、約五十種類の処方を使い分けています。
西洋医学の薬をのむと眠くなったり、喉が渇いたりして不都合な方、抗アレルギー剤を長く服用したくない方、アレルギー体質を改善したい方、妊娠や授乳中の方、漢方薬を服用してみたけど効果がみられない方、身体にやさしく治療したい方…。
お気軽にご相談下さい。