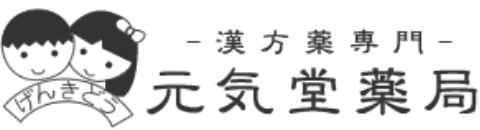VOL.128 生理痛~その5~
中医婦科学によると生理痛は、「痛経」或いは「経行腹痛」と呼ばれ、「月経期或いはその前後に、周期的に出現する下腹部や腰部の疼痛のこと。重症では劇痛となり、甚だしければ昏厥に至ることもある。」と定義されています。
42歳の会社員の方、「生理の後半と生理後に重く引きつるような痛みが下腹から横腹に生じる。痛みは、温めると少し楽になる。食欲は正常だが、疲れ気味で、肩こり、腰痛、眼精疲労がみられる。爪が脆く二枚爪になりやすい。睡眠中に足が攣ることが多い。」といった症状でした。『血虚証』と考え、四物湯と安中散を服用していただきました。過労も生理痛を悪化させていると考え、瓊玉膏も併用しました。1ヶ月ほどで、辛かった生理痛が軽くなり、顔色も良く、元気そうです。
生理痛を漢方的に分類すると、ストレスが痛みを引き起こす『肝気鬱結証』、血液の流れが滞っていることによって痛みを生じる『血瘀証』、辛い物やお酒の摂りすぎによる『実熱証』、反対に冷たい物の摂りすぎや身体を冷やしたことによる『実寒証』、過労などが原因になっている『気虚証』、血液の不足がまねく『血虚証』等々、多種にわたります。
よくみられる傾向としては、桂枝茯苓丸に代表される『血瘀証』に用いる処方ばかりが繁用されており、漢方的な分類により使用されていないため、効果が上がっていない例です。効果を上げるためには、症状の特徴を漢方的に分析、鑑別し、そのタイプの中から更に適した処方を決定していく事が重要です。特に痛みの状態や時期(生理前、生理前半、生理後半など)、悪化条件、好転条件などが肝心になります。